工作機械をレトロフィットしたい・工場の機械の改造に取り組みたいとお考えですか。
本記事では、レトロフィットの定義やオーバーホールとの違い、導入メリット、具体的な工程までわかりやすく解説します。
工場設備の改造やレトロフィットに精通したプロが解説します。生産ラインの効率化や安全性向上、工作機械の長寿命化を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
\ 話を聞いてみたいだけでもOK /
工作機械のレトロフィットとは?オーバーホールとの違いも解説
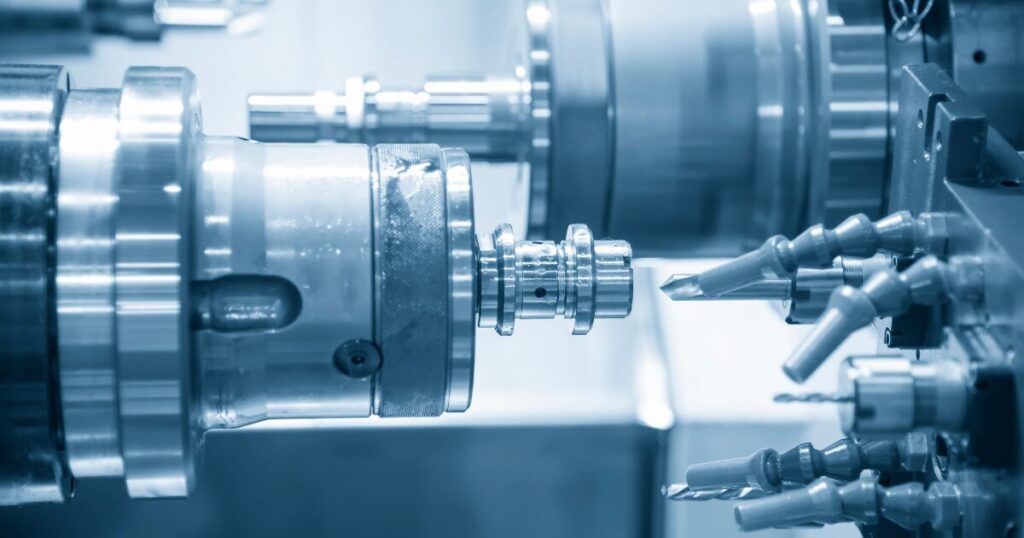
工作機械は長年使い続けることで精度が落ち、部品の摩耗や制御装置の老朽化によって生産効率が低下していきます。新品に買い替えたいと思っても、数千万円から数億円の投資や長納期がネックになることも少なくありません。
そこで注目されているのが「レトロフィット」です。既存機械を活かしつつ性能や機能を改善できる方法として、多くの工場で導入が進んでいます。
ここでは、レトロフィットの定義やオーバーホールとの違い、導入メリットや具体的な工程まで分かりやすく解説します。新品購入か改造かで迷っている方はぜひ参考にしてください。
レトロフィットとは?定義を紹介
レトロフィットとは、既存の工作機械を単なる修理ではなく、最新技術を取り入れて機械そのものをアップグレードすることを指します。摩耗した摺動面やベアリングの交換、主軸の再調整といった修復に加え、NC装置の更新、シーケンサ化、制御盤や配線の入れ替えなどを行います。
結果として、精度や機能が新品同様に復元されるだけでなく、生産性や安全性、保守性が向上し、使い慣れた機械を最新鋭の設備に生まれ変わらせることが可能になります。
レトロフィットとオーバーホールとの違い(費用・目的・効果)
オーバーホールとは、機械を分解して清掃や摩耗部品交換、摺動面の修正などを行い、購入時の状態に復元することが目的です。コストや納期を抑えて精度を回復できる一方で、機能は基本的に据え置きになります。
一方、レトロフィットは現状回復に加えて性能や機能を向上させます。古いNC装置を最新モデルに交換して加工速度を向上させたり、IoT機能を追加して稼働状況をリアルタイムで監視できるようにするなど、現場の課題に合わせた改造が可能です。
費用はオーバーホールより高くなる傾向がありますが、新品導入に比べると大幅に安く、投資回収期間も短くなります。「まだ使えるけれど性能不足」「新機種を買うほどではないが生産性を上げたい」という場合に最適です。
レトロフィットでできることの事例

近年、工作機械の改造案件では「現場の声」に応じてNC装置の更新だけでなく、制御系や安全機能、新技術の取り込みが広がっています。以下は具体的にどのような改造が実施されているかの事例です。
それぞれ見ていきましょう。
NC装置交換・NC化・シーケンサ化
例えば、旧式の工作機械で手動操作やリレー制御しかなかったものに、NC制御装置を新たに取り付けるケースがあります。操作性が大きく改善し、繰り返し加工の誤差も減り、段取り替えの時間も短縮されます。
また、既存のNC装置が古く保守部品の入手が難しい場合、最新のNC装置へリプレースすることで信頼性が向上します。三菱電機FAなどの事例では、制御装置のメモリ容量や処理速度を高めるNCリプレースで、加工時間の短縮や複雑な加工への対応が可能になった例があります。
さらに、手動・汎用機械をNC化することで、人手でのきめ細かな操作に頼っていた工程を自動化し、作業者の負担軽減につながる例もあります。
※出典:MMEG「NC・主軸制御 レトロフィット&リプレース 総合カタログ」
制御装置のアップデートとIoT対応
制御盤の古いリレー回路をPLC(プログラマブルロジックコントローラー)に切り替えたり、操作用のタッチパネルを新設したりする改良がよく行われます。制御信号のレスポンス改善、プログラム変更の柔軟性向上、さらには操作画面の視認性や操作感の向上が期待できます。
IoT技術を導入する事例も増えています。温度・振動・稼働時間など各種センサーを取り付け、リアルタイムに設備の状態をモニタリングすることで故障予知を可能にするものです。
データの蓄積からAIや分析をかけ、最適なメンテナンスタイミングを予測するシステムを取り入れている工場もあり、定期保守から予防保守へのシフトが進んでいます。
自動化・安全対策・精度向上
自動化の一環としてワークの自動搬送や工具交換(ATC)の導入、ロボットとの連携改造などが挙げられます。こうした改造により省力化が進み、人手によるミスが減ります。
工場の自動化について詳しく知りたい人は以下の記事も参考にしてください。
工場の自動化とは?メリット・課題・成功事例・進め方を徹底解説
安全対策としては、防護カバーの取り付けや安全センサーの設置、非常停止システムの最新化が含まれます。古い機械では安全基準が現在の規格に追いついていないことが多く、改造によって現行の安全規格を満たすとともに、作業環境の改善にも貢献します。
精度向上の事例としては、摺動面の修正、ベアリングやガイドレールの交換、主軸の再加工など、機械構造そのものを改良する例があります。
MMEG社の事例には、NCリプレース+主軸モータの交換で加工精度が向上し、生産能率が上がったというデータがあり、加工途中での振動や誤差の低減も確認されています。
※出典:MMEG「NC・主軸制御 レトロフィット&リプレース 総合カタログ」
工作機械のレトロフィットのメリット

レトロフィットを導入することで、ただ古い機械を修理するだけでは得られない複数の利点があります。コスト面・性能面・環境面のそれぞれで、現場や経営にとって有意味な改善をもたらすことが多いです。
それぞれ見ていきましょう。
コスト削減と投資回収期間の短縮
新品の工作機械を購入する際には、機械そのものの価格だけでなく、輸送・据付・試運転などの付随コストや設備の準備が必要になります。レトロフィットなら、これらのコストをある程度抑えることが可能です。既存設備を利用するため、土台や配管・配線など基礎構造をそのまま活かせるケースが多く、導入コストを新品の半分以下に抑えられることもあります。
さらに、投資回収期間(ROI)の観点では、レトロフィット後の省エネや生産性向上、故障低減などの効果によって、2~5年程度で投資を回収できるケースも少なくありません。新品導入と比較しても費用対効果が高く、短期間での設備改善が可能です。
生産性・品質・保守性の向上
レトロフィットにより、工作機械の制御系が最新化されると、繰り返し精度が改善し加工速度が上がることが多くあります。例えば古いNC装置の処理性能が低かったために段取り替えやセットアップ時間が長かった作業が、最新の装置・モーター・ガイド機構の改良で大幅に短縮されるケースが見られます。
品質の点でも、振動や熱変動の抑制、刃物の摩耗の減少など、工程でのばらつきが少なくなるため、製品のばらつき・不良率の低下につながります。保守性という点では、入手困難な部品の代替品対応や国産部品への置き換え、保守履歴を含むカルテ管理などにより、故障発生時の復旧時間を短縮することが可能です。
環境負荷の低減とSDGs対応
既存の工作機械を再利用して改造することは、廃棄物削減に直結します。機械を廃棄せず寿命を延ばすことで、資源を有効に活用できるだけでなく、新規設備の製造や輸送に伴う環境負荷も抑えることができます。
さらに、レトロフィットの際に高効率モーターや最新の制御装置を導入することで、消費電力を削減し、運転コストとCO₂排出量の双方を減らすことが可能です。
また、SDGs(持続可能な開発目標)の観点でも、設備の長寿命化・省エネ・リサイクル推進は企業価値の向上につながります。近年は「エコ改造」や「環境認証」を前提とする補助金制度も増えており、レトロフィットはこれらの要件を満たしやすい施策として注目されています。
工作機械のレトロフィットの流れ・工程

レトロフィットは、単なる修理ではなく計画的な工程を踏んで行われます。現場の課題を明確化し、設計・改造・試運転まで一貫して対応することで、高い精度と安全性を確保します。ここでは一般的な流れを紹介します。
それぞれひとつずつ見ていきましょう。
診断・設計・見積もり
最初のステップは現状の診断です。機械の摩耗状態、制御装置の世代、配線や配管の劣化などを詳細に点検します。必要に応じて精度測定や稼働状況のデータを収集し、どの部分をレトロフィットするべきかを判断します。
次に、目的(NC化、省エネ、自動化など)に応じた改造プランを設計し、仕様書や改造案を作成します。見積もりでは、部品交換費用、制御盤更新費用、工期を明確に提示し、投資対効果(ROI)も検討しやすい形にします。
改造・制御更新・調整
設計と見積もりが確定したら、実際の改造工事に入ります。古いNC装置や電装品を取り外し、新しいNC装置やPLC、配線、配管を組み込みます。
その後、各軸の調整、制御ソフトの設定、デバッグ作業を行い、加工精度が設計通り出ているかを確認します。シミュレーションや試加工を通じて、停止期間を最小限に抑えながら立ち上げを進めます。
納品・教育・アフターフォロー
改造後の機械は現場に再設置され、最終調整・試運転を経て納品されます。納品時にはオペレーター向けに操作説明や安全教育を実施し、新しい制御装置や機能をすぐに活用できるようにします。
納品後も定期点検や遠隔監視による稼働状況のフォロー、故障時の迅速な対応など、アフターフォロー体制が整っているかどうかも重要です。こうした継続的なサポートにより、長期的な安定稼働と設備投資効果を最大化できます。
機械の改造や工作機械のレトロフィット業者ならBRICSにお任せ

株式会社BRICSは、自社工場を持つロボットシステムインテグレータとして、産業用機械の改造や工作機械のレトロフィットまで幅広く対応しています。既存ラインの効率化や安全性向上、制御装置の最新化による精度アップなど、現場の課題に合わせた最適なプランをご提案。
設計から施工、ソフト開発、保守まで一貫して自社で対応できるため、スピーディーかつコストを抑えた導入が可能です。緊急時も即時対応が可能な体制を整えており、補助金申請のサポートも行っています。工場の自動化や設備の長寿命化を検討されている企業様は、ぜひBRICSへご相談ください。
\ 話を聞いてみたいだけでもOK /
レトロフィットに関するよくある質問

機械の改造や工作機械のレトロフィットを検討する際に、多く寄せられる質問をまとめました。導入前の不安や疑問を解消しておきましょう。
工作機械のレトロフィット・修理対応していますか?
株式会社BRICSでは工作機械のレトロフィット・修理に対応しています。おすすめのレトロフィット業者をお探しの方は株式会社BRICSにお問い合わせください。
無料相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
\ 話を聞いてみたいだけでもOK /
レトロフィットの言い換えは?
レトロフィットは「改造」「更新」「リニューアル」「アップグレード」などと言い換えられることがあります。メーカーによっては「NCリプレース」「制御装置更新工事」と呼ばれることもあります。
共通しているのは「現状復帰にとどまらず、機能や性能を向上させる」という点です。単なる修理やオーバーホールと区別して使われることが多い言葉です。
どんな古い機械まで対応できる?
対応可能な年式はメーカーや機種によりますが、30年〜40年前に製造された機械でもレトロフィットできる事例があります。
ポイントは機械本体の剛性やベースの状態が良好であることです。鋳物ベッドや主軸台が健全であれば、電装・制御系を入れ替えることで最新機並みの性能に生まれ変わらせることが可能です。
部品供給が終了している場合も、代替品や国産部品での置き換え、配線図の再設計などで対応可能です。
レトロフィットとオーバーホールはどちらが良い?
選び方は目的によって異なります。
精度を元に戻すだけで良い場合や、コストを最優先したい場合はオーバーホールが適しています。分解清掃や摺動面修正、摩耗部品交換によって新品時の性能に近づけることができます。
一方、古い制御装置を最新化したい、自動化やIoT機能を追加したい、生産性をもっと高めたいといったニーズがあるならレトロフィットがおすすめです。投資額はオーバーホールより高くなりますが、新品導入よりは大幅に安く、機械を長く有効活用できます。
株式会社BRICSではレトロフィット・オーバーホールのどちらも対応しています。自社がどちらが適切か判断したい場合はお気軽にお問い合わせください。
\ 話を聞いてみたいだけでもOK /
まとめ
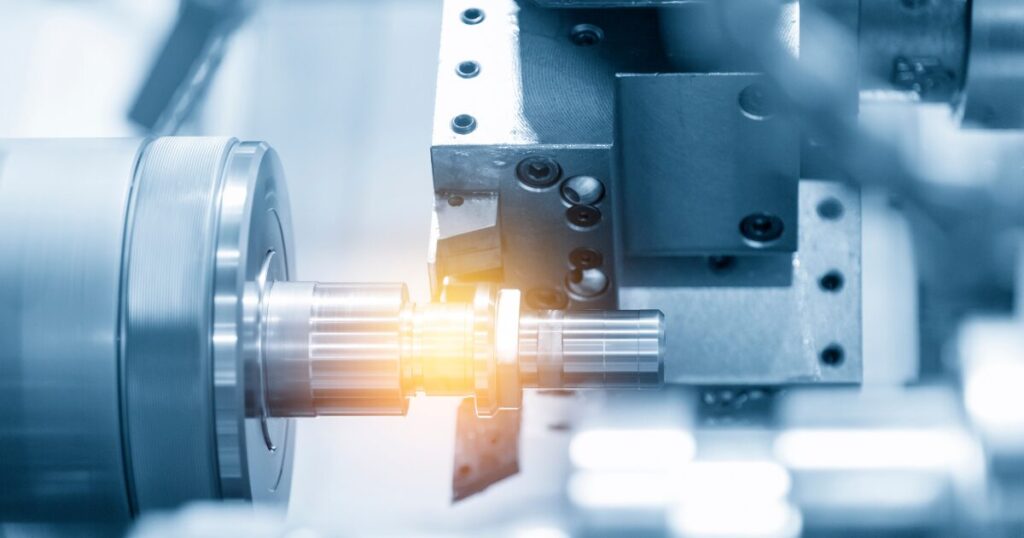
本記事では、工作機械のレトロフィットについて、定義やオーバーホールとの違い、導入メリットや工程を解説しました。レトロフィットは既存機械を最新技術でアップグレードし、生産性・精度・安全性を向上させる手段です。新品購入よりコストを抑えつつ、IoT化や自動化、省エネにも対応できます。
単なる修理ではなく性能強化を目指したい企業に最適な選択肢です。まずは自社設備の課題を診断し、信頼できる業者に相談して最適な改造プランを検討しましょう。BRICSでは毎月5社限定で、無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
\ 話を聞いてみたいだけでもOK /









